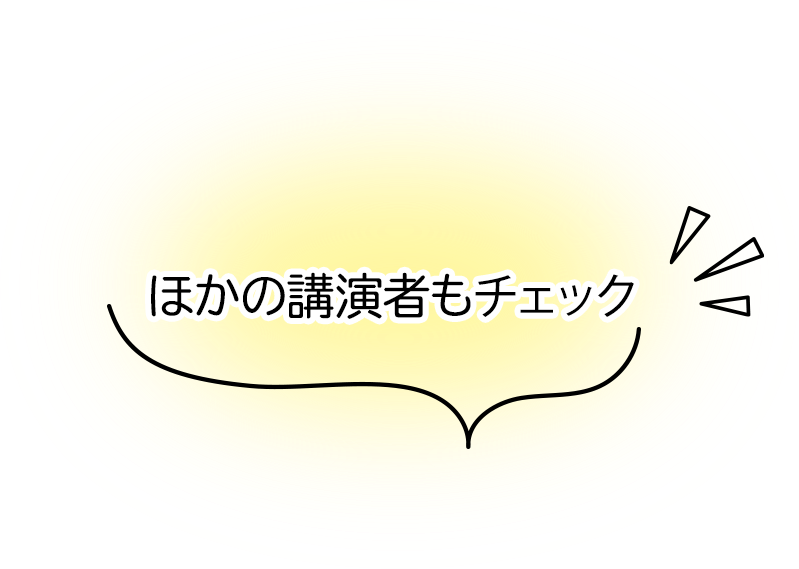野々村 恵子
ののむら けいこ
医生物学研究所 教授

 プロフィール
プロフィール
静岡県で育ち、東京大学薬学部で神経科学研究により博士(薬学)の学位を取得しました。メカノセンシング(機械受容)の未知の生理的役割を明らかにすることを目指し、米国スクリプス研究所、基礎生物学研究所、東京工業大学を経て、2024年4月から京都大学にて研究を進めています。2021年のノーベル生理学・医学賞にも寄与しました。
 もっと詳しく知りたい方へ
もっと詳しく知りたい方へ
学術変革領域研究(B)プレッシオ脳神経科学HP
https://pressio-neurobrain.org/
メカノセンシング生理学分野HP
https://www.infront.kyoto-u.ac.jp/laboratory/lab49/
当日の質問&回答はこちら 録画講演となりました野々村先生に、当日寄せられた質問を回答いただきました。
Q1. どのような学生生活を送られていましたか
熱意ある担任の先生の口癖「踏ん張れ!」に導かれ、地道に勉学を頑張っていました。「高校時代に頑張った記憶」を思い出すと、大学生や研究者になってからも自分はまだまだ底力を出せる!と奮い立たせることが出来ています。また、高校へ通学するバス停からは富士山が綺麗に見えたので、季節や天気による見え方の違いをじっくり「観察」していました。研究者になってからも「観察 (形の特徴を抽出したり、実験群と対照群の違いを見つけること)」が大好きです!
Q2. ご自身の研究の面白さを一言でいうと!
自分達の体の仕組みの精緻さを目の当たりに出来ることです。⽪膚触覚、尿意、呼吸、どれも当たり前のような事柄ですが、その「仕組み」はタンパク質や感覚神経の機能に基づいた「機械受容」に支えられています。我々の研究では、「機械受容」の各臓器における役割と、その仕組みの破綻がどのような病態につながるかのかを調べています。
Q3. 講演でこれを伝えたい イチオシ
「機械受容」の面白さを知っていただき、皆さんにとって当たり前に思えるような体の機能の「凄さ」に気付くきっかけになると嬉しいです。「当たり前のようで、実は世界の誰もまだ理解していないこと」が沢山あります。それに気付くことが、科学の大発見の大きな一歩目です。
Q4. 進路に迷う中学生・高校生の皆様へ
私は中学生・高校生の頃は人生の見通しが立っておらず、漠然とした不安感もありました。大学に入ってから、イキイキと研究に励み「知を楽しむ」研究者ら(大学生、大学院生含む)や自分とは異なる視点や考え方を持つ学友らと出会い、交流することによって、「自分が何を目指したいのか?」や「自分なりの成長戦略」が定まっていきました。大学や社会は楽しいですよ!
Q5. 先生と鹿児島県とのゆかりなどいろいろ(ご出身や旅行での思い出、好物・関心事など)
鹿児島に訪問するのは初めてです。子供の頃から親しくしてきた幼馴染のお母様の出身が鹿児島でして、穏やかで温かいお人柄が育まれた風土に接することが出来るのを楽しみにしています。